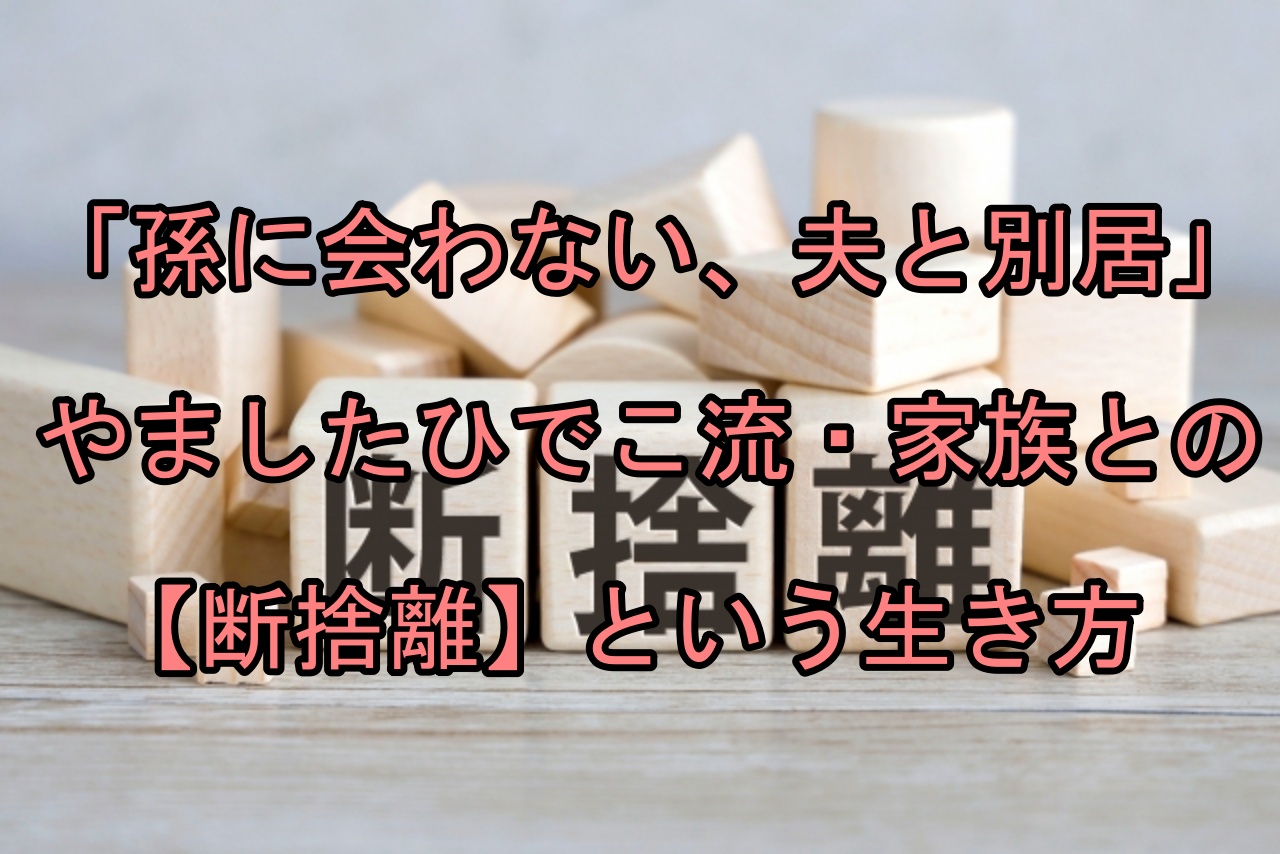※本記事はアフィリエイト広告を利用しています。
「断捨離」で知られるやましたひでこさんは、モノだけでなく人との距離や価値観、さらには死後の形式までも手放すという独自の生き方を実践しています。
複数の拠点で暮らし、家族とは一定の距離を保ちながら、自分の世界をしっかり持って生きる姿勢に、多くの人が驚きや共感を覚えるのではないでしょうか。
私自身、著書を何冊か読んできましたが、最近は「やましたひでこのウチ、”断捨離”しました!」という番組を観るようになり、彼女の思想に改めて惹かれました。
この記事では、やましたさんが断捨離に至った経緯と、その思想の背景、そして実際の暮らし方を紹介します。
私が惹かれたのは、モノを減らすことよりも、自分で選び取ったものに囲まれて生きるという姿勢でした。
やましたひでこさんのプロフィール
- 名前:やましたひでこ
- 生年:1954年生まれ
- 出身:東京都
- 学歴:早稲田大学文学部卒業
- 職業:断捨離提唱者/著述家/講演家
- 経歴:ヨガ哲学をベースに「断捨離」を体系化。著書多数。テレビ・講演活動も精力的。
家族構成と関係性
- 夫:現在は沖縄在住。冬は沖縄、春〜秋は石川県で暮らす季節移動型の生活。別居中だが離婚はしておらず、卒婚的な距離感を保っているようです。
- 息子:ユウキさん。1983年頃生まれ。北海道大学卒業。現在は東京在住で既婚。
- 孫:1人(娘)。やましたさんは「5歳になるまでに3回しか会っていない」と語っています。
家族とは一定の距離を保ちつつ、関係が悪いわけではありません。互いの人生を尊重する姿勢が根底にあるようです。
生活スタイルと拠点
| 拠点 | 特徴・目的 |
|---|---|
| 東京 | 長年の仕事拠点。現在はマンションをダウンサイジングし、より小さな空間へ住み替え |
| 大阪 | 最近マンションを購入。仕事拠点を東京から大阪へ移行中 |
| 沖縄 | 夫の希望で住まいを持つ。冬場の避寒地として活用 |
| 鹿児島(指宿) | リトリート施設「リヒト」をプロデュース。住民票も移し、定期的に滞在 |
やましたさんはこの4拠点を行き来しながら、季節や仕事の流れに合わせて柔軟に暮らしています。
「ひとつの場所に縛られない」「自分にとって心地よい空間を選び取る」という姿勢は、断捨離の思想そのもの。
住まいの選び方にも、“必要なものだけを残す”という哲学が色濃く反映されています。
断捨離思想の原点──ヨガ哲学と“執着”への気づき

やましたひでこさんがヨガ哲学に出会ったのは大学時代のこと。
「心と身体の調和」や「執着からの解放」といった思想に惹かれ、深く学び続けていました。
断捨離という言葉は、ヨガの三つの実践──断行・捨行・離行──に由来します。
不要なものを手放すことで、心の自由を得るというこの思想は、やましたさんの人生観に深く根を下ろしていきました。
モノとの関係性を通して、自分が何に執着しているかに気づく。
それは単なる片づけではなく、心の棚卸しであり、生き方そのものを問い直す行為なのです。
実践としての断捨離──人生の転機と活動の始まり

大学卒業後、夫の実家で義両親と同居する生活を続ける中で、家事・育児・仕事に追われる日々が続きました。
価値観の違いや介護、家族の不幸などが重なり、心身ともに限界を感じるようになったといいます。
50歳を前に「これからは自分の人生を生きる」と決意し、同居を解消。
その後、自ら教室を開いて断捨離セミナーを始めたことが、現在の活動の出発点となりました。
空間としての断捨離──「こまつ町家」の再生

※写真はイメージです
やましたさんの断捨離思想を空間として具現化した象徴的なプロジェクトが、石川県小松市にある「こまつ町家」です。
かつて大量のガラクタに埋もれ、取り壊し寸前だった空き家を、やましたさんがひとりで断捨離し、美しい町家として蘇らせました。
この家は、やましたさんがご自身の母親のために用意したものであり、家族との関係性にも断捨離の思想が反映されています。
「こまつ町家」は、モノを捨てることで空間が蘇り、人の心も整うという断捨離の本質を体現する場所となりました。
※現在、こちらの「こまつ町家」は紹介制の宿泊施設にもなっているようです。
こまつ町家宿泊予約
自分の世界を持つこと──“誰かのため”から離れてみる
やましたひでこさんは、暮らしの中に「自分の世界」を持つことの大切さを繰り返し語っています。
それは、誰かの期待に応えるための空間ではなく、自分自身が心地よくいられる場所をつくるということです。
彼女は、断捨離を通じて「自分軸で生きる」ことを提唱しています。
モノの選び方、空間の使い方、人との距離感──すべてにおいて、自分がどう感じるかを基準にする。
その結果として、他者との関係もより健やかで、無理のないものになっていくのだと語っています。
この考え方に触れることで、「誰かのために整える部屋」ではなく、
「自分が満たされる空間」を持つことの意味を、静かに見つめ直すようになりました。
自分の世界を持つことは、わがままでも孤立でもなく、自分を大切にするための第一歩なのだと感じます。
家族との距離感──“近すぎず遠すぎず”の心地よさ

やましたひでこさんは、家族との関係においても「断捨離」の思想を貫いています。
それは、関係を断ち切るという意味ではなく、過剰な期待や依存を手放し、互いの自由を尊重するという姿勢です。
夫とは現在、別居という形をとっています。
この選択は、関係の破綻ではなく「自立した個としての共存」を目指すもの。
やましたさんは「一緒に暮らすことだけが家族の形ではない」と語り、距離を保ちながらも穏やかな関係を築いています。
かつては同じ空間に暮らしながら、互いの価値観や生活リズムに違和感を覚えることもあったといいます。
その違和感を無理に埋めようとせず、「距離を置く」という選択をしたことで、むしろ関係が穏やかになった。
「物理的な距離が、心の余白を生む」──それは断捨離の本質にも通じる考え方です。
また、孫に関しても「5歳までに3回しか会っていない」と公言しています。
その理由について、やましたさんは「自分のことで忙しいから、会いたいとは思わない」と語っています。
この言葉には、家族だからといって常に近くにいるべきだという固定観念を手放す潔さが感じられます。
私自身も、息子たちとは離れて暮らしています。
一緒に暮らしていた頃よりも、今のほうが関係が穏やかで、互いに心地よく過ごせているように感じます。
家族と一定の距離を置くことは、冷たさではなく、自分自身を大切にするための選択であり、相手の人生を尊重する姿勢でもあるのだと思います。
やましたさんの考え方には、私も共感するところがあります。
家族とは、いつも一緒にいることが大切なのではなく、ちょうどいい距離を保つことが、お互いにとって心地よい関係につながるのではないでしょうか。
死後の形式に縛られない思想──“生きた証”の残し方
やましたひでこさんは、死後の形式についても、一般的な慣習にとらわれない考え方を示しています。
著書『よりよく生きるための断捨離式エンディング・ノート』などで、「お墓はいらない」「葬儀も必要ない」と語り、自分の死を誰かに委ねるのではなく自分で選び取るという姿勢を貫いています。
彼女は、死後の形式にこだわるよりも、生きている間にどう生きるかを重視しています。
モノを手放すことも、空間を整えることも、すべては「今ここを生きる」ための準備であり、
その延長線上に、死を迎えるときの自由さや軽やかさがあるのだと語っています。
この思想に触れることで、「死とは終わりではなく、選択のひとつなのかもしれない」と感じるようになりました。
形式に縛られず、自分らしく生き、自分らしく去る。
その静かな覚悟に、深い共感を覚えます。
よりよく生きるための断捨離式エンディング・ノート
まとめ
やましたひでこさんの暮らし方に触れることで、私自身の中にあった「こうあるべき」という前提に対する違和感が明らかになり、それを認められた気がしました。
モノとの関係、家族との距離、空間の使い方、そして死の迎え方──
どれも誰かに決められるものではなく、自分で選び取ることができるのだと気づかされます。
断捨離は、単なる片づけではありません。
それは、自分の内側にある「執着」や「思い込み」と向き合い、今の自分にとって本当に必要なものだけを残すという、静かな選択の連続です。
やましたさんの思想に共感するのは、そこに自由と責任が同居しているからかもしれません。
誰かのためではなく、自分のために生きること。
それはわがままではなく、他者との関係をより誠実にするための土台だと思います。
この暮らし方に惹かれるのは、私自身が自分軸で生きたいと願っているからです。
モノの少なさではなく選び取ったものの確かさによって、自分らしさを支えてくれるのだと思います。