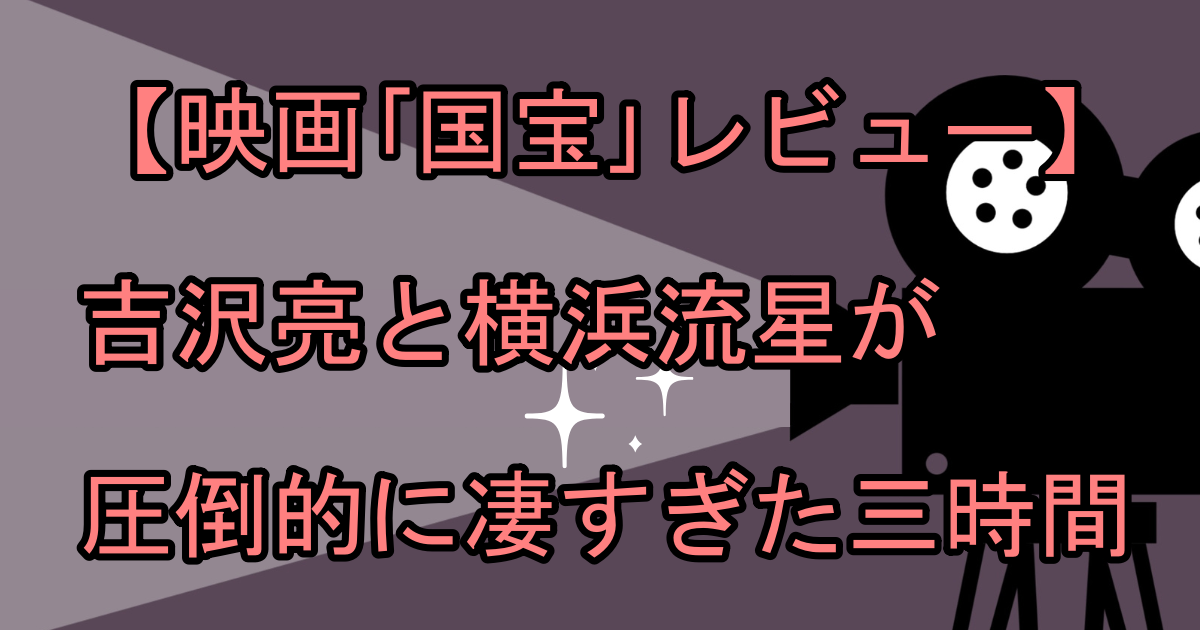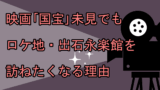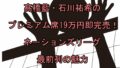映画「国宝」を観てきました
この映画、迷っているなら絶対に観るべきです。
原作は途中で挫折し、歌舞伎の知識もゼロ。
主演のイケメン俳優2人にも特別な推し感情はなかった私が、数年ぶりに映画館へ足を運ぶほど惹かれた作品です。
劇場鑑賞のすすめ・上映時間について
「映画館まで行くほどのものかな…?」と観る前は迷っていました。
上映時間は3時間。正直、お尻は痛くなりました(笑)
でもそれ以上に目がスクリーンに釘付けで、長く感じる暇がありませんでした。
夜の回で客層は若者が多く、「歌舞伎映画にしては意外」と思いましたが、観終わって納得。
それだけ“観る理由”がちゃんとある映画です。
吉沢亮と横浜流星の圧倒的な存在感と演技力
主演の吉沢亮さんと横浜流星さんが画面に映っている時間が長く、
その美しさと演技力は圧倒的です。
喜久雄と俊介の高校生時代を演じた子役の黒川想矢さんと越山敬達さんも印象的で、
主演ふたりに似た雰囲気や表情、仕草から将来の二人を彷彿とさせ、キャスティングの巧みさに感心しました。
特に吉沢亮さんの女形の姿は妖艶で神々しいほど。
「喜久雄と俊介、配役逆じゃない?」という声もありますが、私は断言します。
吉沢亮さんが喜久雄を演じることで、この作品が成立していると思います。
本作は間違いなく、吉沢亮さんの代表作として語り継がれるでしょう。
ストーリーは“芸に殉じた男たち”の生き様
物語は、喜久雄の父が亡くなるその日の宴の場面から始まります。
多感な時期に差しかかった喜久雄が極道の家の現実と向き合う衝撃的な幕開けです。
父の死をきっかけに喜久雄は歌舞伎役者の家に引き取られ、
そこで同い年の俊介と出会います。二人は親友でありライバル。
芸にすべてを捧げ、時に落ちぶれ、時に這い上がりながら生きていく。
血のつながり、友情、信頼と裏切り、スキャンダル、栄光。
彼らの人生が複雑に絡み合いながら進んでいきます。
歌舞伎の演目だけでなく、複雑な人間関係や歌舞伎界の闇までが濃密に描かれており、3時間では足りないと感じるほどの壮大な物語です。
映画が“初めての歌舞伎”体験に
私は生の歌舞伎を観たことがありません。
まさか映画が私の“初・歌舞伎体験”になるとは思いませんでした。
歌舞伎の魅力に圧倒されました。
外見の美しさだけでなく、所作の一つひとつに心を奪われます。
演じているのは俳優ですが、
主演の吉沢亮さんと横浜流星さんは1年半もの間、稽古を積み重ねてこの役に挑んだそうです。
その努力を想像するだけで、尊敬の念を抱かずにはいられません。
歌舞伎ファンからは物足りなさの声もありますが、
舞台裏や役者の視点で描かれる演出は、映画ならではの魅力だと感じました。
脇を固める俳優陣も名演揃い
主演二人の演技には圧倒されました。
ドラマや大河で見たことがあっても、ここまで“役に生きている”姿は初めて。
鬼気迫る演技で、目の動き、息づかい、声の震えまで感情と直結していました。
渡辺謙さん、寺島しのぶさんといった名優が重厚さを加え、
高畑充希さん、三浦貴大さんらも丁寧に役を演じていました。
演技のぶつかり合いをスクリーンで体験できる、貴重な映画です。
3時間で語りきれない壮大な物語──だから原作を読みたくなる
気になった点としては、場面転換の早さと唐突さ。
父親が殺され、復讐未遂、引き取られ、女性との関係、子どもの登場…
「○年後」というテロップで次々場面が移り変わります。
時間制約もあり仕方ないですが、
「もっとこの部分、深く見たい」と感じる場面も多かったです。
映画で芽生えた“物足りなさ”を原作で補いたくなる、そんな作品です。
観る前に迷っている人へ:絶対に観て損はない映画です
原作を途中でやめた、歌舞伎に詳しくない、主演俳優に特別な推しがいない…
そんな私でも心を揺さぶられました。
美しさ、苦しさ、愛、執念。
単なる「芸の物語」ではなく、「人生」を描いた作品です。
迷っているなら、ぜひ劇場で観てください。
観終わった後の余韻をじっくり味わってほしいです。
関連記事
映画を観る前に書いたロケ地の記事はこちらからどうぞ。